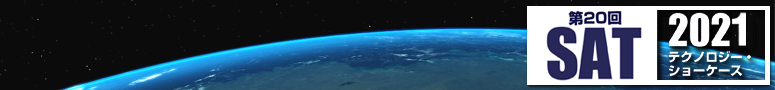特別シンポジウム
地球観測衛星と新型コロナウイルス感染症
16:00〜18:00 オンライン開催
【スケジュール】
| 16:00~ | 第1講演 濱本 昂氏 |
| 16:20~ | 第2講演 塩見 慶氏 |
| 16:40~ | 第3講演① 山地 萌果氏 |
| 17:00~ | 第3講演② 大原 美保氏 |
| 17:20~ | 休憩 |
| パネル討論 | |
| 17:30~ | 濱本 昂氏、塩見 慶氏、山地 萌果氏、大原 美保氏 (座長)宇宙航空研究開発機構 理事・筑波宇宙センター所長 寺田 弘慈氏 |
特別講演
「コロナ影響把握のための衛星データ解析における国際連携」
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行は世界中の人々の日常生活に対して大きな困難をもたらし、社会経済活動や地球環境に対して様々な変化を引き起こした。この感染症による影響を把握するため、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は米国航空宇宙局(NASA)、欧州宇宙機関(ESA)と協力して大気質、気候、商業活動、農業、水質の分野で地球観測衛星データのCOVID-19流行前後の解析を行い、2020年6月25日にこれらの解析結果を可視化したwebサイト「Earth Observing Dashboard」を立ち上げた。本講演では、この3つの宇宙機関による国際連携の概要と得られた解析結果について紹介する。【講演者】

濱本 昂(はまもと こう)氏
宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門衛星利用運用センター研究開発員
講演者の略歴
2013年、北海道大学理学院宇宙理学専攻修士課程修了。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)入社。入社後、地球観測研究センターにてアジアにおける地球観測衛星の社会利用研究・実証に携わった後、アジア開発銀行に出向し途上国開発事業への衛星利用促進に従事(2017〜2020年)。現在、衛星利用運用センターにて、地球観測衛星に関わる国際協力推進を担当。
「GOSATによる温室効果ガス観測にみるコロナの影響」
温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(いぶき)は2009年から運用を開始して、現在10年を超えて、宇宙から二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)といった、温室効果ガス濃度の観測を実施している。GOSATはその特徴を生かして、大規模CO2排出源である大都市を集中的に観測し、約10kmの対流圏高度を2層に分離することにより、排出源に近い低層のCO2濃度データを取得できる。COVID-19流行のなか、人間活動が抑制されることによる人為起源CO2濃度の微量な変化は宇宙から捉えられるのか、その解析結果を紹介する。【講演者】
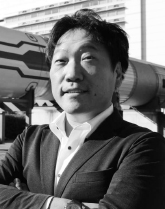
塩見 慶(しおみ けい)氏
宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門地球観測研究センター/GOSAT-2プロジェクトチーム
主任研究開発員
講演者の略歴
2001年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。リモート・センシング技術センターを経て、2007年、宇宙航空研究開発機構に入社。入社後、温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(いぶき)シリーズのデータ利用研究を担当している。宇宙からの温室効果ガス観測を2009年GOSAT-1号機により開始し、二酸化炭素濃度データの取得とその精度向上に努めている。2018年からは後継機GOSAT-2号機の観測運用も担当。
「withコロナ時代の地球観測衛星を活用した災害対応」 ①JAXAにおける災害への取り組み
衛星による地球観測の大きな意義の一つとして、人が直接現地に行かなくても、遠く離れた宇宙から地球の表層の状態を把握できることがあげられる。withコロナ時代の災害対応という観点からも、このような衛星による”リモート”観測の重要性が改めて認識されてきている。本講演では、激甚化している水災害に着目し、JAXAで開発・提供している衛星全球降水マップ(GSMaP)を活用した水災害分野での利用事例について紹介する。【講演者】
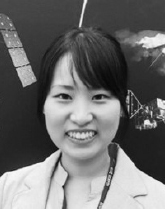
山地 萌果(やまじ もえか)氏
宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門地球観測研究センター 研究開発員
講演者の略歴
2015年、東京都立大学大学院都市環境科学研究科地理環境科学域博士前期課程修了。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)入社。入社後から一貫し、地球観測研究センターにて、全球降水観測(GPM)計画や衛星全球降水マップ(GSMaP)の研究開発・利用研究に従事。アジア太平洋地域をはじめとする衛星降水データの利用推進も担当。
「withコロナ時代の地球観測衛星を活用した災害対応」②西アフリカ諸国での衛星観測雨量を活用した洪水監視・予測システムの展開とコロナ禍での災害対応研修
土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)は、UNESCOプロジェクトとして、西アフリカのニジェール川・ボルタ川を対象として、衛星観測雨量を活用した洪水監視・予測システムを開発・運用するとともに、想定される洪水シナリオに基づく災害対応タイムライン立案方法に関する現地関係者への研修を展開している。研修は当初は対面研修を予定していたが、コロナ禍によりeラーニング研修に転換し、現在までに100名を超える研究修了生を輩出した。本講演では、本プロジェクトの活動を紹介する。
【講演者】

大原 美保(おおはら みほ)氏
土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター
主任研究員
講演者の略歴
専門は災害リスク評価・マネジメント。東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻修士課程・博士課程で学んだ後、博士号(工学)を取得。東京大学生産技術研究所及び東京大学総合防災情報研究センター准教授を経て、2014年に国立研究開発法人 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)主任研究員に着任。政策研究大学院大学防災学プログラム連携准教授として、途上国の行政職員の教育・研修にも従事。中央防災会議防災対策実行会議、国土審議会国土管理専門委員会、文部科学省科学技術・学術審議会防災科学技術委員会等に委員として参加.地域安全学会年間優秀論文賞(2015)、日本地理学会賞(論文発信部門)(2017)等を受賞。
パネル討論座長
【座長】

寺田 弘慈(てらだ こうじ)氏
宇宙航空研究開発機構理事・筑波宇宙センター所長
座長の略歴
1985年東京大学工学部航空学科卒業後、宇宙開発事業団(現宇宙航空研究開発機構)に入社、技術試験衛星「きく6号、8号」の開発などに従事。 2007年からは準天頂衛星プロジェクトマネージャーを務め、2010年みちびき初号機打上げ成功に貢献。広報部長、経営企画部長、調達部長、衛星システム開発統括・衛星測位技術統括を務めた後、2020年4月より現職。